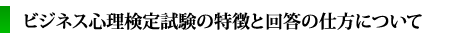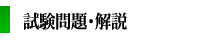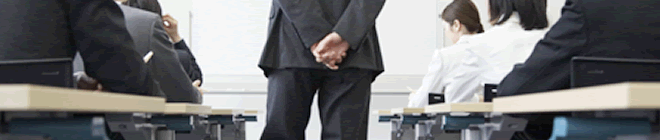
ビジネス心理検定の初級コースはマークシート形式による4択式の問題が50問です。前半25問程(20〜30)の範囲は基本問題であり、後半25問程(20〜25の範囲)は応用問題となっています。
各問題に対して均等に2点配分となりますので、前半の基本問題25問は確実に点を採るようにし、後半の応用問題(25問)は具体的な現場での状況を理解したうえで解くようにすることが肝要です。
- まず、基本問題のマークシートの例題1からみていきましょう。
■例題1
次の文章を読み、カッコの中に当てはまる用語の適切な組み合わせを選びなさい。
言語表現には、習慣的に決まっている文字通りの意味があるが、聞き手は言語表現を聞いたとき、その文字通りの意味を理解したうえで、話し手の意図を理解しようとする。このとき、生じる言外の意味をグライスの( A )という。
たとえば、夏の暑いときに部屋に招かれたとき「窓を開けてほしい」と言いたいとすれば、直接そう言うのではなく、( B )といった表現でそれを示すことが多い。ただし、話し手の意図が文字通りの意味なのか、含意なのかは、その発話の状況によって判断しなければならないだろう。
A / B 1) 会話の含意 / 窓が開けもらえるとうれしいのですが 2) 暗黙知 / 今日も暑いですね 3) 会話の含意 / 今日も暑いですね 4) 暗黙知 / 窓が開けもらえるとうれしいのですが
(*注:3番が正解)●ポイント1
これは用語を中心とした「穴埋め式」の問題です。用語も基本的な概念を意味する者しか出てきませんので、あまり細かい学者の名前など覚えておく努力はしなくてもよいわけです。
マークシート式の問題は初級も中級も4択式の問題ですが、テキスト『ビジネス心理』を一通り読み理解しておけば解けるものです。テキストの中で、とくに太字で示された用語の意味を知っているかがポイントになります。まずは内容そのものの理解に努めるようにしてください。
-
次に、同じく基本問題のマークシートの例題2ですが「不適切」なものを選ぶタイプです。
■例題2
「ビジネス心理の5原則」の説明した文章で不適切なものを一つ選びなさい。1) “個”を全体システムの機械的な部分なのではなく、全体の特質を反映したダイナミックは過程とみなすものが「創発性」である。 2) 多様な人の理解と共感をみ出すリソースが情報・データではなく、人の“声”や感情が反映された物語的なものとするのが「対話性」である。 3) 人の強みと弱みの両面をその当人の在りたい姿への成長発展の中で捉えていく視点が「快活性」である。 4) 職場の協働作業が学びそのものを生成していくとする理論とも関連するものが「証拠性」だ。
(*注:3番が正解)●ポイント2
この例題2では「不適切な」という条件なので注意が必要ですが、適切か不適切かは全体の半分ずつ程です。
この種の問題は「正解」が客観的にあるわけではなく、比較するとどこか現実や理論とのズレがあるため、消去法でやっていくほうがよいでしょう。
-
それでは、応用問題のマークシートの例題を検討してみましょう。
■例題3
次のサービス虚偽表示の事件についての文章を読み各問いに応えなさい。
最近、有名ホテルや百貨店が虚偽のサービスをしていたことで問題となっています。伊勢エビと思ってホテルで食べたものが、半額以下の別のエビであったといった事件です。
これは安いものに切り替えた時点で店頭の表示を変えるべきだったわけですが、その原因は顧客軽視というコック側の心理が問題なのでしょうか?
事件に至る背景を全体としてみると、そうではないようです。それは表示をする仕事がコックの“分断された作業”になっていたことが問題だからです。
コック当人の“役割意識”では、“料理を作る”が自己の責任を持つ内容であり、それ以外のことは自分の”役割“だとは意識していなかったことです。コックにすれば、表示の変更は販売・営業担当らの仕事としてみなしていたのだと考えられます。
だから、ここで優先すべきは、適切な“表示”を顧客にするという行動をさせる意識にすること。より正確にいえば、自分の“役割意識”としてコック側の( A )を変えることなのです。
この点でお手本となるのは、ディズニーでの「キャスト」という名称で( B )をネイミングとしてアルバイト達に与えた方法です。それによって、アルバイト達が名実ともにディズニーらしい行動になったということです。
□問い1
カッコのAに当てはまる用語で適切なものを選びなさい。1)自尊感情 2)アイデンティティ 3)自己開示 4)性格
(*注:2番が正解)□問い2
カッコのBに当てはまる用語で適切なもの選びなさい。1)主役 2)ブランド 3)役割意識 4)社会意識
(*注:3番が正解)●ポイント3
例題3の「問い1」では、E・エリクソンの「アイデンティティ」(「自己同一性」ともいわれる)、そして問い2は「役割意識」が正解です。 文の前後を読めば適切な用語が選べるものです。
検定試験では応用なので社会情勢を反映したような論説文や商談や顧客との対話場面などがよく取り上げられます。
応用は指定の公式テキスト『ビジネス心理』の範囲だけに限定されないため、ある程度は教養的な要素やビジネス現場での経験的な知識が必要なものも出題されます。
- では、中級検定の問題例を検討してみましょう。
まずはマネジメント心理の専門分野の基礎問題からです。■例題4
M・セリグマンは、楽観的な説明スタイルはよいことが起きた時と悪いことがおきたときである、明確な傾向があることを実証した。そこで、二つの表を参照して次の問いに答えなさい。
楽観的説明スタイル 悲観的説明スタイル 自他の軸 自己の責任 他者の責任 時間軸 ( A ) ( B ) 空間軸 全面的 限定的 < 表1:物事がうまくいった時の説明スタイルの違い >
楽観的説明スタイル 悲観的説明スタイル 自他の軸 自他の境界が明確 自己主体 時間軸 一時的 永続的 空間軸 ( C ) ( D ) < 表2:物事がうまくいかない時の説明スタイルの違い >
上記のカッコに入る用語の組み合わせについて、適切なものを選びなさい。
A / B / C / D 1) 永続的 / 一時的 / 限定的 / 全面的 2) 一時的 / 永続的 / 限定的 / 全面的 3) 永続的 / 一時的 / 全面的 / 限定的 4) 一時的 / 永続的 / 全面的 / 限定的
(*注:1番が正解)●ポイント4
例題4は、ポジティブ心理学の特徴をどんな説明スタイルをとるかという点から比較したものです。
公式テキスト第2巻『ビジネス心理(マネジメント編)』の366〜367頁に掲載されている比較表を使用した問題です。このように図解や表になっているものは、とくに重要な内容なのでよく理解しておくようにしてください。
成功や失敗したときにどんな“言い訳”をするかが大事なポイントです。悲観的な人は成功しても他人や周りの環境のせいにしてしまうわけで、その当たりの理由を整理して理解しておくことが必要です。
- 次に中級検定の応用問題例を検討してみましょう。
まずはマーケティング心理の専門分野の応用問題からです。■例題5
次の「購買行動」に関する文章を読み、各問いに答えなさい。
消費者の購買行動は、消費者が自身の欲求に気づくことから始まる。消費者にとって、欲求が満たされていない状態は、心理的な不快感や緊張感をもたらすため、欲求が満たされた理想の状態と現実の状態とのズレを認識すると、そのズレを解消しようと動機づけられる。このような消費者の購買行動をとくに( A )という。
消費者が欲求認識をしたあと、基本的な購買意思決定プロセスでは、情報探索、代替案評価、購買決定、購買後評価の段階を経るとされている。しかし、購入する商品によっては、基本的な購買意思決定プロセスの一部が省略される( B )のパターンが見られたり、ほとんどのプロセスが省略されてしまう場合もある。
□問い1
( A )にあてはまる適切な用語を選びなさい。1)意思決定行動 2)不協和低減行動 3)問題解決行動 4)妥協案探索行動
(*注:3番が正解)□問い2
上記の文章の( B )にあてはまる適切な用語を選びなさい。1)習慣的問題解決行動 2)包括的問題解決行動 3)ルーチン的問題解決行動
4)限定的問題解決行動(*注:4番が正解)●ポイント5
例題4の「問い1」では、消費者の購買行動がどんな心理的プロセスでおこなわれているかを問うものです。消費者はあまり意識しないで購入するような習慣行動のレベルと、自覚的によく考えて購入していくような異なる行動タイプがあります。しかし、いずれも何らかの問題解決をしているという点では共通するものです。そこで回答は「問題解決行動」となります。
考えすぎて「不協和低減行動」を選ぶかもしれませんが、これは「認知的不協和」という行動と認識とのギャップを解消しようとするものです。これは買った後などでその商品が良いものだと思いたいようなことから自己正当化をしてしまうようなケースであり、ある特別な問題解決の状態を指すものなのでここには当てはまりません。
「問い2」で問うているのは、習慣で買う日常品や安い商品などの場合の購買行動の特徴であり、分析はせずに省略的な意思決定をする場合ということです。そのような行動の特徴は「限定的問題解決行動」と云います。 ここは「習慣的問題解決行動」も回答として選ぶ可能性もありますが、それですと習慣的なものだけを取り上げている場合になり回答としての妥当性が低いことになります。