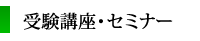<<ACT���r�W�l�X�S���u���i�F��j�̂��ē�>>
<<ACT���r�W�l�X�S���u���i�F��j�̂��ē�>>
�i�H�G9���`11���ɂ킽��S12��̔F��u���j
�uACT���r�W�l�X�S���u���v�i�S12��^�e3���Ԓ��j�́A���{�r�W�l�X�S���w��ł̌����Ǝ��H������S���Z�@���U�̃e�[�}�Ōv12��s�����̂ł��B����͎��H�I�Ɠ����Ƀr�W�l�X�S�����莎���̔F��u���ł����邽�߃|�C���g�t�^�������̂ł��B
���A�����i�V�h�E�a�J�j�����łȂ��A�u���̋L�^���悪�����̕�����u���ł��܂��B�U�l�܂ł̏��l�����Łh�Θb�h�i�_�C�A���[�O�j���d�˂Ă��������ł���A���ꎩ�̂����݃R�[�`���O�ɂ��Ȃ���̂ł��B����I�Ȃ��ƈȏ�ɁA�Q�������o�[�̑��݂̌��i�i���e�B�u�j����w�тƂ�u���ꉻ�v�̗͂ɒ��͂���u���ł��B
���̃��\�b�h�̃L�[���uACT�v�i�A�N�Z�v�^���X���R�~�b�g�����g�E�g���[�j���O�j�ł��B����͑�O�̔F�m�s���Ö@�Ƃ��Ăꂽ�gACT�h�i�������́gT�h�̓Z���s�[�j�ƁA����Ƀv���X���āu�X�L�[�}�Ö@�v�i���X�L�[�}�Ƃ͔F���̘g�g�݂̂��Ɓj��l�ވ琬�E�g�D�J���ɓ���������̂ł��B���̓�̌������r�W�l�X�S���w�ɉ��p�������{���̍u���ł��B
���e�u���̏ڍׂ͎��y�[�W��育�Q�Ƃ��������B
- 09/06�ߑO�i��P��j�^�w�u�l+�g�D�v�̐f�f���́E�c�[���ҁx�i�O���j
- 09/06�ߌ�i��Q��j�^�w�u�l+�g�D�v�̐f�f���́E�c�[���ҁx�i�㔼�j
- 09/27�ߑO�i��R��j�^�w�ڋq���̓}�b�v�ҁx�i�O���j
- 09/27�ߌ�i��S��j�^�w�ڋq���̓}�b�v�ҁx�i�㔼�j
- 10/18�ߑO�i��T��j�^�w���O�o�c�c�[���u�N���h�v�ҁx�i�O���j
- 10/18�ߌ�i��U��j�^�w���O�o�c�c�[���u�N���h�v�ҁx�i�㔼�j
- 10/19�ߑO�i��V��j�^�w�g�D���v�̂��߂̖ڕW�Ǘ��ҁx�i�O���j
- 10/19�ߌ�i��W��j�^�w�g�D���v�̂��߂̖ڕW�Ǘ��ҁx�i�㔼�j
- 11/08�ߑO�i��X��j�^�w�`�[���n��̂��߂̃R�[�`���O�S���ҁx�i�O���j
- 11/08�ߌ�i��10��j�^�w�`�[���n��̂��߂̃R�[�`���O�S���ҁx�i�㔼�j
- 11/15�ߑO�i��11��j�^�w�s����U������u�i�b�W�v�ҁx�i�O���j
- 11/15�ߌ�i��12��j�^�w�s����U������u�i�b�W�x�ҁx�i�㔼�j
���ڂ����u�����A���̃y�[�W�����Q�Ƃ��������B
■���u������u���邱�Ƃɂ�郁���b�g�Ɠ��T�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
✔���T�P�F���l��6�l���^���Ȃ��Ă��L�^����Ŏ����^������̓�̔\�͈琬
���u���͏��l���U�l���ōu�t�Ƃ̑Θb�^�ɂ��w�т���{�Ƃ��Ȃ���A�J�[�h���p��}�b�v�������čŐV�̐S���w�̐��ʂ������ɉ��p�ł���悤�\�����Ă��܂��B�܂��A�`�h���l�Ŋ��p�ł���悤�ɂ��邽�߂o�b���Q�i�s���ӂȕ����t�H���[�j�ƂȂ�܂��B
�܂��A���̍u�K�L�^���悪��������i��u�҂͖����^�l�b�g�����݂̂̕����艿5�������j�ł���̂Ō��Ȃ��Ă����S�ł��i���Q���҂̉f���͎B��܂���j�B�Ƃ��Ɍo�c�E�l����c�ƁE�L���̃R���T���^���g�E�R�[�`���߂��������Ɠ��Ő��ɖ𗧂Ă������ɍœK�ł��B
���̂��߂ɁA�u���ł͂Ƃ��Ɂu���ݒ�́v�Ɓu�T�O�\���́v�i���L�[���[�h�̊֘A�������j�̈琬���d�����Ă��܂��B���̓�̔\�͂��r�W�l�X�S���̉��p�͂����߂���̂�����ł��B
✔���T�Q�F�F��u������ƌ��荇�ۂ̃|�C���g���_���t�^
���u���ł�1�u����3���Ԃ�P�ʂɂ��Ă���2�_���̃|�C���g���_�����܂��B���莎���̎҂͐\��������۔��莞�Ɏ����̓_���ɉ��Z�������̂ł��B
✔���T�R�F�㋉����R�[�X�ւ́u��ы������v������@���������B
�F��u����30�|�C���g�ȏ�̉i��15��j�܂Ŏ��ꍇ�A�����E�����������ɏ㋉����i�ʐڎ����̂݁j���u��ы��R�[�X�v�Ŏ邱�Ƃ��ł��܂��B
✔���T�S�F��u�����Z�b�g�����Ɋ������^�����̕��͋L�^����̎����݂̂��i5�������j
��u���i�ō��݁j�͂P�u��=¥8,000�A�R��܂Ƃ߂ẴZ�b�g�����ɂ���R�������̊e¥5,600�A�U��܂Ƃ߂̃Z�b�g�����ł͂T�������̊e¥4,000�ƂȂ�܂��B
�@�܂��A�����Ń��A���u���ɎQ���ł��Ȃ����͋L�^���悪��L�̏����̂���Ɋe5�������ŃZ�b�g�����ł̎������ł��܂��B�i��F3��܂Ƃ߂Ŋe2,800�A�e6��܂Ƃ߂ł͊e¥2,000�j
�@�w���͂���ɏ�L�̈�ʂ̃Z�b�g���i�ȂǑS�Ĕ��z�Ƃ��܂��B�i��F���A����u6�Z�b�g�Ŋe¥2,000�j�B�܂��|�C���g���_�͋L�^���掋���݂̂ł����l�ɕt���܂��B
 �y�u�t�z���@�p��
�y�u�t�z���@�p��
���{�r�W�l�X�S���w���^���f�W�^���n���E�b�h��w����
�F��r�W�l�X�S���㋉�}�X�^�[�A���{���̔F�m�Ȋw���̃R���T����Ђ𓌑��w���̌����҂��1990�N�ɑn�݂��A�A�b�v���Ђ�Z�F�RM�Ȃ�100�Јȏ�̃R���T���ɏ]���BTV�o���������B
�S�Ă̍u���ɂ킽�����w���E�R�[�`���O�����Ă����܂��B
 �y���u�t�z�r�@���q
�y���u�t�z�r�@���q
�F��r�W�l�X�S���㋉�}�X�^�[�A���L�����A�R���T���^���g�A�Y�ƃJ�E���Z���[�A�t�@�C�i���V�����v�����i�[�̗L���i�҂Ƃ��ă����^���x���̋Ɩ��ɏ]���B
�e�u���ŁA�`�[���w�K�ȂǕK�v�ɉ����ăT�|�[�g���Ƃ��ĒS���B
���@ACT�r�W�l�X�S���u���̓��e�̏ڍׂ��ē��@��
���e���̏��͍ʼn��i�̃y�[�W�ɂ܂Ƃ߂ăA�N�Z�X�ȂNjL�ڂ��Ă��܂��B
���u���ԍ��F25B1
●09/06�i�y�j�ߑO���^10:15�`12:45�y���z�݉�c���w�����X�y�[�X�V�h�U�x
�wACT���r�W�l�X�S���u���i��P��j�^�u�l+�g�D�v�̐f�f���̓c�[���ҁx�i�O���j
�@���i�f�f��K���f�f�A�����đg�D�̃��W���G���X�f�f�ȂǐS���w�̐f�f�@�ɂ͗����Ɨ���������������A���̌�����m��Ȃ��Łh�q�ϓI�Ȃ��́h�ƐM������ł��܂��Ǝ��s���܂��B���̌����I�Ȗ��ƍ��킹�ăC���^�r���[�⎿��̊�ݒ�Ȃlj�������̑ΏۂɓK���A���̐f�f�́h�R�g�o�h�ɒ��ڂ��ė��p�̍œK�ȕ��@�����i���\�h���W�[�j���w�т܂��B
�u������E�C�v��TV�h���}�ɂ��Ȃ����t���C�g�ƕ��ԃA�h���[�̐S���Ö@�ł́A�u���i�f�f�v�ɑ��Ĕے�I�ł��B�u���i�v�Ƃ������̂����̎��_�ŌŒ艻���Ĕ��f���Ă��܂����X�N������ƍl���邽�߂ł��B���i�������ɓ��v�I�ȑÓ����̂���`�Őf�f���ꂽ�Ƃ��Ă��A���ꂪ���̎��_�ł̐Î~���������ł��邱�Ƃɕς��܂���B
����Ȃ��Ƃ���A�r�W�l�X�S���w�ł͐��i��\�͂Ƃ������Ƃ��u�]�����f���v�Ƃ݂Ȃ��A����́uEQ�v��m���́uIQ�v�ƁA����ɐl�ԊW�⓹��Ƃ̊W���́uSQ�v��s���͂́uAQ�v�_���t�������Ă��܂��B�����̂S�͕č��o�c�w�҃��`���[�h�E�V�F���������u�E�I�[�g���X�N�[���̖{���̐����̎��Ɓv�ł��Љ�Ă�����̂ł��B
����ɉ����ĖړI�́uOQ�v�����������̂��r�W�l�X�S���w��ŊJ�������u�TQ�v�̃��f���ł��B���́gO�h�́uObject�v�i�Ώہj�ł���g�߂������́h�Ƃ����Ӗ��ł����A�A�h���[��h���b�J�[�̖ړI�u����\�͕]���_�ɑg�ݍ����̂ł��B���Ƃ��A�l�����������̗p�ʒk�ł̎�ȐS���o�C�A�X�ɂ͎��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B
- ����̊O���I���͂ɂ��]���̘c��⇒EQ�o�C�A�X
- �G���g���[�V�[�g�̎g�����ɂ��c��⇒SQ�o�C�A�X
- ���Ђ̗��O�Ȃlj��l�ӎ��Ƃ̂���⇒OQ�o�C�A�X
���u���ԍ��F25B2
●09/06�i�y�j�ߌ㕔�^13:15�`14:45�y���z�݉�c���w�����X�y�[�X�V�h�U�x
�wACT���r�W�l�X�S���u���i��Q��j�^�u�l+�g�D�v�̐f�f���̓c�[���ҁx�i�㔼�j
�u�d���͐f�f�v�i�r�W�l�X�S���w��ďC������ɂ��Ȃ���A�u�T�p���f���v�̊�ƁE�w�Z�ł̑g�D���v�Ȃǂ̐����E���s���������Ȃ���A���̋�̓I�Ȋ��p���@�ƃ��^�t�@�[���g�����f�f���e�̗����̌��ʂɂ��Ċw�т܂��B
�����݂̍���ɏd���������I�[�v���ȁu�����u���v�Ȃ̂��A�����I�Ȉ����_�T���̃N���[�Y�ȁu���u���v�Ȃ̂��B���������헪�I�Ȕ��f��̔F������n�܂�A���Ђł̐V�����f�f�@��z�肷�邱�ƂŁA�B�ꂽ��肪�����яオ���Ă��܂��B�Ƃ��ɂ��́h��h���ǂ����������S���I�Ȃ��̂��A�f�f���̂��̂����d�����Ă���_�ɓ���������܂��B
�K�E�f�f���f���̕W���Ƃ��ăz�[�����h�́u�E�ƓK�����f��CPS-J�v�́A���E�I�ȓK���f�f�@�ł��B����́u�l�I�Ȑ��i�v�Ɓu�E�����v�Ƃ��ǂ̒��x�}�b�`���Ă��邩�Ƃ����E�Ƃ̓K���x�����߂�Ƃ�����̂ł��B�u�t�̏��p�ꂪ���@�J���������i��i2010�N���j�ł́A���̃z�[�����h���������E�E�V���C�����́u�L�����A�E�A���J�[�v�̎��_��g�ݍ���œK���x����������@���J�����Ă��܂��B�����6�̃p�[�\�i���e�B�E�^�C�v��6�p�`�ŕ\��������̂ł��B
���̓����Ƃ��ẮA①�Z�p�`��ׂ̗荇������(�Ⴆ��Љ�I��Ƣ�|�p�I�)�͂ƂĂ��ގ����Ă���B②�Z�p�`��̔��Α��Ɉʒu���镪��(�Ⴆ��Љ�I��Ƣ�����I�)�͍ł����݂̗ގ��_�����Ȃ��B�����������e���p�^�[���Ƃ��Ď���ɑΉ������ăl�b�g��œK���f�f��������̂ł������A���̐f�f�́u�v�̖��_�Ȃǂ����Č������Ȃ���l�b�g���p�̗����ƃ��X�N��S���w�I�ɗ������Ă����܂��B
���u���ԍ��F25B3
●09/27�i�y�j�ߑO���^08:30�`11:45�y���z�݉�c���w���[��B�x
�wACT���r�W�l�X�S���u���i��R��j�^�ڋq���̓}�b�v�ҁx�i�O���j
�ڋq���ǂ�ȍw���̌���ʂ��Čڋq�����ă��s�[�^�ւƂȂ���̂��B���̃v���Z�X���}�b�v�ɂ������̂��u�J�X�^�}�[�E�W���[�j�E�}�b�v�v�ł����A���̋�̓I�ȊJ���E���p�@�ɂ��Ă̌������������܂��B�Ƃ��Ɍڋq�����x�i�b�r�j���������������c�ƁE�̔��̃v���Z�X�͂��Ă݂�ƁA�߂������ʂƖ����̎w�W����т������̂ɂȂ炸�g���[�h�I�t�i�����j�̖�������Ă��܂��Ă��܂��B���̉ۑ��ACT���ڋq���͂��ǂ��𗧂����J�X�^�}�[�E�W���[�j�������Ȃ���w�т܂��B
����V�j�A�̒j���q���Ȃ̒a�����Ȃ̂Ő����t�̂��郌�X�g������\�čs�����Ƃ��̂��ƁB�����w�r���̍ŏ�K����݂���i�͂��炵���A�����ʼn̂��Ȃ���f�B�i�[���y���߂�͂��ł����B�Ƃ��낪�A�X�̒����t�߂̋q�Ȃ͒c�̋q�݂̑����ԂŁA�h��Ȕ����j���ʼn̂Ȃǒ����l�q���Ȃ��A�����B�̘b�Ő���オ���Ă��܂��B����͂��q���̃}�i�[�̖��ł��傤���B
�@���{�I�Ȗ��́A���̃��X�g�������̌ڋq�ւ̃T�[�r�X�ςɂ���܂��B�����t�������ė����A�q�ƈꎞ�I�Ɋy���ޒc�̋q�A���̏ꍇ�́g���l�h���ǂ��ɋ��߂邩�ł��B�V�j�A�q�́u�����t�̉́v�����Ă����Ǝv���ė����̂ł����A����ȕ��͋C�ł͂���܂���B����Ȃ狏�����ł��������Ƃō������X�g�����ɗ���K�v�͂���܂���B�X���ɂ���A�c�̋q�͔���ɍv�����邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B�������A�����t��厖�ɂ�����g��������h�p���ɏ�A�̃��s�[�^�q�͂��Ă���ł��傤���H
�r�W�l�X�ł͕K�������������������g���l�h�̑I���𔗂����ʂ�����܂��B���̂Ƃ��ɑ厖�Ȃ��Ƃ͉������l�i���O�j�Ƃ��Čڋq�ɒ��邩�������̂ł��B���̈Ӗ��Łg���O�h�Ƃ͂������������锭�z�Ƃ͈Ⴂ�܂��B���̃��X�g�����́A���ꂪ�u���Ă��܂��Ă����̂ł��B
���u���́A�܂����������ڋq�̑̌��v���Z�X���}�b�v�����Ȃ���A���̌ڋq�̐S���ω���F�����A�Ԃ�Ȃ��T�[�r�X�E�̔��̎�@���K�����Ă������e�ł��B
���u���ԍ��F25B4
●09/27�i�y�j�ߌ㕔�^13:45�`17:45�y���z�݉�c���w�����X�y�[�X�V�h�U�x
�wACT���r�W�l�X�S���u���i��S��j�^�ڋq���̓}�b�v�ҁx�i�㔼�j
�쐬���ꂽ�J�X�^�}�[�E�W���\�j�E�}�b�v�̗��p������łǂ̂悤�ɐi�߂���̂�������ƍ��킹�Č������Ȃ���A���̂j�o�h�w�W�Ƃ̓����I�Ȏ��_����ۂ̌ڋq�s���̉��P�v�����i���[�h�Ǘ���i�[�`���[�Ǘ��j���������Ă����܂��B�Ƃ��Ɂu�ڋq�R�~���j�e�B�v�̊��������ȂLj��Ƃ��z�����ڋq���_���{������e�ł��B
�ڋq�����ɑ傫�ȉe����^����̂́A���̌ڋq�́u�������ҁv�Ǝ��ۂ̗��p��̏[�����̃M���b�v�ł��B���̃M���b�v���ǂ����߂�悢���Ƃ������Ƃ��ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B���̕��@���u���҃}�l�W�����g�v�ł���A�����Ɍ����q���̊��҂��h�œK�Ȃ��́h�ɂ��邩���d�v�ɂȂ�܂��B����͏��i�̗ǂ��_�̒�Ă����邾���łȂ��A�����_��\�ߏ����̒i�K�ł�������`����悤�ɂ��邱�Ƃ�����ł��B
�@�ꌩ����Ƒ��肪�s�����ɂȂ邩������Ȃ��ƕs���Ɏv���܂����A����������Ē����I�Ȏ��_�ʼn䖝����̂ł��B�܂�A�u�����x�v�́g���ΓI�h�Ȃ��̂ł����Ċ���ς��Γ��������ł��h�s���h�ɕς��̂ł��B�����āA���̂悤�ȕ]���@���u����s���f�f�v�Ɠ���ł͌ĂсA�u���҃M���b�v�����V�[�g�v�̍쐬�@����Ă��܂��B���u���ł͂��̍쐬�̌��������łȂ��A���Ђ̎��H�v���Z�X�ɉ������S�̃C���[�W�𗝉����Ă��炦��悤�w�ԓ��e���\�����Ă��܂��B
���u���ԍ��F25B5
●10/18�i�y�j�ߑO09:45�`13:15�y���z�݉�c���w�����X�y�[�X�V�h�U�x
�wACT���r�W�l�X�S���u���i��T��j�^���O�o�c�c�[���u�N���h�v�ҁx�i�O���j
�@�g�D�����o�[�̉��l�ς���v�����A�o�c���O�ɂ������s�����Ƃ�ɂ́u�N���h�v�Ƃ���蒠���́h�����h��h�h�̕������L���ł��邱�Ƃ�������Ă��܂��B�������f���ƂȂ鑼�Ђ̗��O�o�c�̎��H������w�тȂ���A���Г��L�̗��O���f�����쐬����v���Z�X�Ő��܂�Ă����Q�┽�Έӌ��Ȃnj������܂��B�����āA�g�D�E�l�̉��v�݂̍�����܂߂����O�̎��Ӌ`����ʂ̐S���w�I�ȗv���Ɛ����̏������w�т܂��B
��Ƒg�D�̗��O�≿�l�́g�R�g�o�̌�����h�̓����ɂ͎��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B
- �o�c�҂̎v������̃R�g�o
- �Ј��ɌP�����邽�߂̕W��Ƃ��ẴR�g�o
- �V���I�ȏ��g�D�������p�����邽�߂̈��k���ꂽ�R�g�o
���u���ԍ��F25B6
●10/18�i�y�j�ߌ㕔13:45�`16:15 �y���z�݉�c���w�����X�y�[�X�V�h�U�x
�wACT���r�W�l�X�S���u���i��U��j�^���O�o�c�c�[���u�N���h�v�ҁx�i�㔼�j
�@�N���h������̑g�D�݂̍�����e�[�}�i��F�S���I���S�����j�쐬���Ȃ���A���̐S����p�╶�Ă̍쐬�@�ɂ��Ă`�b�s���́u�N���[�������Q�[�W�v����w�т܂��B�u�N���[�������Q�[�W�v�̓R�g�o�̈Ӗ���]�����������_��ɂ��錾�ꉻ�̃��\�b�h�ł��B���̃J�[�h���̌��ꉻ�̕��@���g���Ȃ���N���h�̊��p�@���K�����܂��B
���u���ł́u�N���h�v�̍쐬�ƕ��͂�ʂ��ăR�g�o�̎��S����p�Ƃ��̗L�����������𗝉����A���H�̕��@���K�����܂��B���Ƃ��A���̂悤�Ȏ��Ј��Ƃ̃R�[�`���O��ʂ�z�肵�܂��B
�@�R�[�`�F�N���h�ɏ����ꂽ�w�L���C���߂����x�Ƃ́A�ǂ�ȊC�ł����H
�@�Ё@���F���̊��o�ł͔g�͉��₩�ŁA�ł������ɐV��������������Ƃ��������ł���
�@�R�[�`�F���́w�V�������x�ɂ́A��������܂����H
�@�Ё@���F����Ɛ����̋@�����C�����܂��B
���������N���h�ɏ����ꂽ�R�g�o��}��ɂ����Θb�̉ߒ��ł́A���`�I�ȈӖ����z�����C���[�W������A�Θb���͂��݂܂��B�����āA���̔�g�I���E�̒��őI���̕����L����T�����J��Ԃ����Ƃ��ł��܂��B���������v�l�̒T���ł́A�������^�t�@�[���Ȃ���Ζ��̂��鈫�����T����펯�I�ȓ����ς������A�Ό��ȂǂŐ�������Ă��܂��܂��i���Q�Ɓj�B���̂悤�ɁA���u���ł́u�N���[�������Q�[�W�v�̎�@���������āA�J�[�h���̃}�b�v�����s���Ȃ���N���h�쐬�@�Ƃ��̓��e��[�߁A�Θb����w�тƂ�ACT���̔\�͂��K�����Ă����܂��B
���u���ԍ��F25B7
●10/19�i���j�ߑO��09:45�`12:15�y���z�݉�c���w�����X�y�[�X�V�h�U�x
�wACT���r�W�l�X�S���u���i��V��j�^�g�D���v�̂��߂́u�ڕW�Ǘ��v�ҁx�i�O���j
�����ACT���̖ڕW�Ǘ��ɂ��āA�ȉ��̂悤�ȁu�ُؖ@�v�̊����̊ϓ_����ړI�u���^�̑g�D���v���w�т܂��B
①�l�E�g�D�̉��l�i���O�j�ւ̈�ѐ��^②�g���邪�܂܁h�̐l�E�g�D����e���^③�����̂��߂ɍ����]���ɂ��Ȃ����H���^④�ے�I�Ȃ��̂̒��ɍm��I�Ȏ��̐������݂�W�]���B
���̂悤��ACT���̊Ǘ��ł́A���l�i�Ӌ`�j�̗����ɂ܂����ԂƘJ�͂������܂��B���̎��ɖ��_�ƂȂ���̂�T���A����ɋC�Â��K�v������܂��B����͖������̈�ʓI�Ȏ菇�ɂ݂��܂����A�l�K�e�B�u�Ȋ�������邪�܂܂Ɏ~�߂�_���قȂ�܂��B��������ʂӂ肷��̂ł͂Ȃ��A���̂܂܌�������킯�ł����A�����͂ǂ����Ă�����I�ɔr�������萳�����������Ȃ��Ă��܂��܂��B�Ȃ��Ȃ�ߋ��̑̌��̒��Œ~�ς���Ă����v�����݁i�X�L�[�}�j�����������邩��ł��B�������蕥���Ƃ����s�����S�Ԗڂ́u�E�t���[�W�����v�Ȃ̂ł��B
- ���l�̖��m���iValues�j �~ �Ј��̓��@����
⇒�Ј��j�[�Y�����Ј��̉��l��D�悵�u�Ј��ɂƂ��Đ^�ɑ�Ȃ��͉̂����v���番��
- ���݂ւ̋C�Â��iPresent Moment�j �~ �d���̕�������
⇒�Ј����d�����鍡���̂̐S����Ԃ��u���ݎu���v�ő���Wellbeing���[��������
- ��e�iAcceptance�j �~ �Ј��̕s�����R�̗���
⇒�Ј��́u�l�K�e�B�u����v��ے肹���Ј��̖����d�����Ǘ��v- �E�t���[�W�����iDefusion�j �~ �ߋ��̌o����v�����݂̒E�p
⇒�ߋ��̕s���⎸�s�ɂ��u�v�����݁v����̉���𑣂����b�Z�[�W�v- ���ȂƂ��ẴR���e�N�X�g�iSelf-as-context�j �~ �Ј��̖����ϗe
⇒�Ј����u���Ȃ̕ω��v�u�V���ȃA�C�f���e�B�e�B�v���ł���- �R�~�b�g���ꂽ�s���iCommitted Action�j�̍s���x��
⇒�Ј�������̒��Ŏ����炵���̉��l�ɉ������s�����p���ł��� �ȏ�̓��������������`�ŁA���Ђ̑g�D�����ɉ������ڕW�Ǘ��̎��H���@���K�����Ă����܂��B���u���ԍ��F25B8
●10/19�i���j�ߌ㕔12:30�`15:15�y���z�݉�c���w�����X�y�[�X�V�h�U�x
�wACT���r�W�l�X�S���u���i��W��j�^�g�D���v�̂��߂́u�ڕW�Ǘ��v�ҁx�i�㔼�j�@�h���b�J�[�̖ڕW�Ǘ��̎��_�����A����ɂ`�b�s���}�l�W�����g�@�͌l�����l�Ɋ�Â��čs�����A�����v�l�ɏ_��ɑΉ�����͂�ڕW�Ǘ��ɏ_��Ɋ������S����@�ł��B���̖ڕW�Ǘ��@�����H�̏�ł͂ǂ�ȉۑ�▵�����N����̂��𗝉����A���̑Ή��E��֘A����g�D���v�̎���ƕ��@�̋�̍���w�т܂��B
�y�ڍׁz�����̊�Ƃł͖ڕW�Ǘ��iMBO�j�����{����Ă��Ă��A�l�̃Z���t�}�l�W�����g�ƂȂ���Ȃ����ߎ��H�����̉��P�Ɏ���Ȃ��P�[�X����������܂��B�u�t�̃R���T�����Ƃ□�̑f�Ђ́u�p�[�p�X�o�c�v�̎��ᕪ�͂���A�h���b�J�[�����������Z���t�}�l�W�����g�Ƃ̊֘A�������̎��_����K�����܂��B
- �ڕW�Ǘ����߂����{���́g�p�[�p�X�h�Ƃ͉���
- �g�D�����i���y�j�̐S���A�Ƃ��Ɂu�����S���v���y�ڂ����X�N�Ƃ͉���
- �Ј��̃G���Q�[�W�����g�i�d���ւ̔M�Ӂj���p�[�p�X�ɂ�荂�߂���@�͉���
- �u�E���ڕW�v=����̃l�K�e�B�u�ȍs���̒��ŁA�ӎ����ꂸ�ɐ��ݓI�ɉe����^����ڕW�̂���
- �u���t���N�V�����v=�ڕW����Ȃ���͂ł���A�R�g�o�Ƃ��Ă����łȂ������g�̊��o�ւƌq������
- �u�ڕW�����V�[�g�v=�|�̃E���ڕW���{�ɂ��邽�߂̓Ǝ��V�[�g�i�r�W�l�X�S���w��ďC�j
���u���ԍ��F25B9
●11/08�i�y�j�ߑO��09:45�`12:30�y���z�݉�c���w�V�h�t�H���X�g�X�y�[�X�x
�wACT���r�W�l�X�S���u���i��X��j�^�`�[���n��̂��߂̃R�[�`���O�S���ҁx�i�O���j����܂ł̃R�[�`���O�͌l�P�ʂł̔\�͎�`�ł���A�������u�X���́v���x�X�g�̂悤�Ɏv���Ă����o�܂�����܂��B�������A�����߂��Ă���͓̂�l�ȏ�̃`�[���P�ʂł̉��l��`�Ƃ������ׂ��ω��������Ă��܂��B���̐V��������͐S���w������̒��ł́h�h�i�d�g�݁E���x�I�ȕ������u�j�ł݂�K�v���ƈ�̂ƂȂ��Ă���A�`�[���n�肪�V���ȑ����ŏd�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă��܂��B������ACT�����ǂ�Ȍ��ʂƐ��ʂނ̂��A��̓I�ȁu�X�L�[�}�E�J�[�h�v�i���{�r�W�l�X�S���w��ďC�j�Ƃ�����@�ő���̐S���s���̊�{�p�^�[���𗝉�������@���w�т܂��B
�y�ڍׁz�R�[�`���O�ł͌X���͂Ƃ��������Ƃ��w���̌����Ƃ݂Ȃ���Ă��܂��B�ł����A�����ɂ͂悭�����Α��肪�g�C�Â��h�Ǝv�����ތ��������܂��B�����ł͂Ȃ��A����ƃR�[�`�̊W���̒��ɂ��鐬���ւ́g���\�[�X�h�A��������o����Ă鎟�̗͂��琬�̗v�ƂȂ���̂ł��B
- �u�����}�C���h�v=���K�I�Ȑ��ʂ����߂�ȏ�ɐ����X�e�b�v�ɂ������}�C���h�Z�b�g
- �u�f�q�hT�v =�g��蔲���́h�Ƃ����T�O�ŁA����ȖړI�ւ̌p�������s�����Ӗ�����
- �u�v���ӎ��v =�h���b�J�[���u�v���t�F�b�V���i���̏����v�ł̎d���̈Ӗ��Â��������
���u���ԍ��F25B10
●11/08�i�y�j�ߌ㕔13:15�`16:15�y���z�݉�c���w�V�h�t�H���X�g�X�y�[�X�x
�wACT���r�W�l�X�S���u���i��10��j�^�`�[���n��̂��߂̃R�[�`���O�S���ҁx�i�㔼�j�R�[�`���O�̎��ۂ̏�Łu�N���[���E�����Q�[�W�v�Ƃ�����@���猩�����Ă����ƁA�����Ɍ݂��̃R�g�o�̎��͂̌����F���̘c�݂������オ���Ă��܂��B��l���y�A�ɂȂ莩���̌��R�g�o����Ř^����������Ȃ���A���̑Θb�̒��ł�����R�g�o�̃Y���͂��Ă����܂��B�܂��A�����̎����ʂ�ݒ肵�āA�݂��̌��łǂ�ȗD�ʐ�����낤�Ƃ���̂����K���܂��B����ɂ��A�����ɂƂ��Ă̏펯�I�R�g�o�i���i���e�B�u�j���l�ɂǂ��������e����^���A�܂������ɒ��˕Ԃ��Ă��邩�ɋC�Â����ƂɂȂ�̂ł��B
�y�ڍׁz�u�N���[�������Q�[�W�v���悭�g���̂̓��^�t�@�[�i��g�j�ɂ��Ӗ��̓]���B�������A���ꂾ���łȂ��A�������ߋ��ɂ��邱�Ƃɂ���āA���̓��e���ߋ��ɂ��������Ƃ��Öق̑O��ɂ�����@�Ȃǂ�����܂��B�����͒Z���S���Ö@�̃~���g���E�G���N�\�����g���Ă������̂ł��B�Ƃ��Ɍ��`����ߋ��`�ւ̓����ϊ��͉B�ꂽ�S�����ʂ������炷���̂��Ƃ����܂��B���b����R�~���j�P�[�V�����̃v���Z�X���̂��A������s����ɂ݂��ߋ��́u���������́v�ւƓ]�����Ă�������ł��B����͌��ȏo�����⎸���ȂǐS���I�ɗ������ޓ��e�ɑ��Ē��������Ă��܂���@�̈�Ƃ����܂��B
���Ƃ��A�u���A�������ċꂵ��ł���̂ł��v�Ƃ����R�g�o���u�����ł����B�h���������h���Ƃ���A�h�ꂵ��ł����h��ł��ˁv�Ƃ����悤�ɓ������ߋ��`�ɂ��Ă��܂��B���̌��ʂƂ��āA�R�g�o��Ԃ��ꂽ����͈Öقɉ߂��Ă��܂������ۂւƔF����]�����Ă��܂��킯�ł��B
�@�������������^�́g���t���[���h�i�Ӗ��]���j�̕��@�͌���̌������ߋ��▢�����t�]���Ĉ�x�ʂ̎��_���甭�z�]�����Ă݂���̂ł��B����ɂ���āA���Ȃ݂̍���̋�����Œ�I�ȖʂɋC�Â��ĉ����ɂȂ���Ƃ����킯�ł��B���u���ԍ��F25B11
●11/15�i�y�j�ߑO��09:45�`12:30�y���z�y���z�݉�c���wKS1�V�h�䉑�x
�wACT���r�W�l�X�S���u���i��11��j�^�s����U������u�i�b�W�v�ҁx�i�O���j�h�i�b�W�h�iNudge�j�͍s���o�ϊw�Œm����悤�ɂȂ����L�[���[�h�B����͖]�܂����s���ɗU��������d�|������邤���Łu���������ƂȂ���́v�Ƃ����Ӗ��ŏd�v�ł����A����������{���̐S���w���痣��ēƂ�������Ă��܂��B����͂ނ���F�m�Ȋw�̍őO���ɂ�����e�Ȃ̂ł����A�܂��͐�������łǂ�ȃi�b�W�̗��p�ɂ��r�W�l�X���ʂ����܂�Ă���̂�����̓I�ȕ��͂Ńp�^�[���ނ��Ă����܂��B����ƁA�F�m�o�C�A�X�Ȃǐ����������Ă��Ă��A�����ɋ��ʂ���S���I�@�����͈ӊO�ɏ��Ȃ����Ƃ��킩���Ă��܂��B
�y�ڍׁz�u�i�b�W�iNudges�j�v�Ƃ̓m�[�x���o�ϊw�܂����S���w�҃��`���[�h�E�Z�C���\�炪2017�N��������s���o�ϊw�̃L�[���[�h�ł��B���̊T�O�͔F�m�Ȋw�́u�A�t�H�[�_���X�v���x�[�X�ɂȂ��Ă���A����l�̏K���s��������̉��P�Ȃǂɕs���ȃ��\�b�h�ɂȂ��Ă��܂��B�i�b�W�̌��`�́u�I�ŕt���v�Ƃ������Ӗ��ł���A������x�s���̑I�����u���ƂȂ����Ă��܂��v�悤�ȁg�d�|���h��m�̂��Ƃ��Ƃ����܂��B���̃i�b�W�́u�킩���Ă��邯��ǂ�߂��Ȃ��v�悤�ȏK���s����ς���̂ɂ��L���ł��B���Ƃ��A�j���g�C���̕֊�̐^�Ƀn�`�̊G��I�ɂ���`�ŕ`���Ƃ������H�v���킩��₷���i�b�W�̓T�^��ł��B
�l�̍s����ς���h�i�b�W�h���d�g�݉�������@�ɂ́A����̍s���ω����N��������������T�����Ƃ��|�C���g�ɂȂ�܂��B������J��Ԃ��K���I�ȍs���ł���A�ʁE���̂����ꂩ��10���ς��Ă݂ĕω��������Ă݂�̂ł��B
�@���u���ł͂��������ς������K���s���̓T�^�p�^�[���ނ��A����ɉ������s���]���̎d�����g�i�b�W�h�̎��̂R�̎��_����J�[�h�E�}�b�v�ɂ��čl�Ă��܂��B
- �u����s���v=�����O�́g�����ȍs���h�ɕω����N�����ƍs���S�̂��ς��
- �u�̍č\���v=�����s���́g�����h�łȂ��A�悢�s���ɂ���g�]���h���s��
- �u�����鉻�v =�ǂ��s�����ӎ��E�p�������邽�߂ɓ���̍s���ω����u�����鉻�v����
���u���ԍ��F25B12
●11/15�i�y�j�ߌ㕔13:15�`16:15�y���z�y���z�݉�c���wKS1�V�h�䉑�x
�wACT���r�W�l�X�S���u���i��12��j�^�s����U������u�i�b�W�v�ҁx�i�㔼�j�g�i�b�W�h�̌����̌����Ƃ������ׂ��A�u�A�t�H�[�_���X�v�Ƃ����F�m�Ȋw�̊T�O�𗝉����邱�Ƃ��d�v�ł��B���̍l�����������p���邤���ŁA���m�Ɛl�̑��ݍ�p�̕����I�ȐS���̓������r�W�l�X���ꂩ�玖��͂��Ă݂܂��B���u���ł̓i�b�W���̃m�E�n�E���u�����I�A�t�H�[�_���X�v�Ƃ��ĐV���ɑ̌n�Â��A���p�͈͂̍L���\�͂̏K����ڎw���܂��B
�y�ڍׁz�u�i�b�W�v�ɂ���ē��l���ӎ����Ȃ����炢�ɓ�����O�ɂ���s���ɂȂ�킯�ł����A���́h������O�h�i�����̕W���j�Ǝv�����ʂ��u�f�t�H���g���ʁv�ƌĂ�ł��܂��B���̓T�^�Ⴊ�l�b�g�ŃT�v�������g�����̔��̎�@�ŁA�f�t�H���g�Ƃ��āu✔�v����ꂸ�ɁA���̂܂܃N���b�N����Β���w���ł���d�|���ɂȂ��Ă��܂��B
����͒ʏ�̃i�b�W�̌����ɂ�郁�\�b�h�ł����A���̈ӎ����Ȃ��Œ����ɂł���g�펯�h�i�R�����Z���X�j�ɂ��s���ɖڂ�����ƁA�����ƕ����I�ȗv�������������@�����邱�Ƃ��ŋߒ��ڂ���Ă��Ă��܂��B
���Ƃ��A�č��̃g���^�Ђɂ͎Г��̈�p�ɐ_�I��u��������������Ƃ����܂����A���̐_�I�����邱�Ƃɂ���ĎЈ���̍s�����_���Ȃ��̂ւ́g�h�Ӂh�ɂȂ���悤�Ȃ��Ƃ��N���܂��B�����œ��u���ł́A���̕����I�Ȏ��_����̃i�b�W�̎�@��Ǝ��ɊJ�����A�s���o�ϊw�̋����i�b�W�_���z�����u�����I�A�t�H�[�_���X�v�Ƃ�����������Ă��܂��B
�����ł�����`����Ɓu�����I�ɋ��L���ꂽ�Ӗ��≿�l�����̒��ɖ��ߍ��܂�A�g�s���\���h�Ƃ��Ēm�o�����v�Ƃ������̂ł��B��������s�����P�́u�����I�d�g�݉��v���l�Ă��Ă������ƂŁA���Ƃ��u����v�����S�����ʂȂǁA���{���L�̕����S�����r�W�l�X�Ɋ��������@�Ȃǂ��K���ł�����e�ƂȂ��Ă��܂��B�E�E�E�E�E�E�E�y�e�u�����̖��̂ƃr���ƒn�}�̏��z�E�E�E�E�E�E�E�E�E
★�݉�c���w�����X�y�[�X�V�h�U�x
�V�h��V�h5����18��20�� ���b�N�n�C�c�V�h401�����@���V�h�O���ډwE1�o����20�b
https://www.spacee.jp/pre_bookings/share/d9388de23d4f45f0a750876a63362882
★�݉�c���w�V�h�t�H���X�g�X�y�[�X�x
�V�h��V�h5����18��20�� ���b�N�n�C�c�V�h707�����@���V�h�O���ډwE1�o���k��20�b
https://www.spacemarket.com/spaces/ntax_eklxttfpend/
★�݉�c���w���[��B�x
�a�J��a�J2-22-7 ���h�r��5�K
https://www.spacee.jp/pre_bookings/share/3f8b9b475300483f81414900085d07be
★�݉�c���wKS1�V�h�䉑�x
�����s�V�h��V�h1-15-6�@�I���G���g�V�h10�K1004���� KS1��c��
https://goo.gl/maps/9NogsZPwgQx7gftJ8 - ��e�iAcceptance�j �~ �Ј��̕s�����R�̗���
 �y���z�FZOOM���̌�����^��S���j19���`21��
�y���z�FZOOM���̌�����^��S���j19���`21��
���r�W�l�X�S���A�J�f�~�[��
�y���e�z ����͎����̖����Q����OK�ł��B�u�t���E�R�����^�[���͓�����i���p�ꎁ�^������b�q���j�A�������ŎQ�������o�[���w��Q�l���̓��e�����|�[�g���\���A���̓��e���u�t������BZOOM���̂��߁A������V���Ɋw�K�ł��闘��������܂��B
������ł��邽�ߔN���Q���i�ō��݁j�����ł��Q���ł��܂��B���l�����ł��̂ŁA���S���ċ^��_�ȂǏڂ����w�Ԃ��Ƃ��ł��A���ꂼ��̎Q�������o�[�Ƃ̓��c�E�𗬂��e���ɂł��܂��B�����āA����́u�F��v�Ȃ̂œ��_�|�C���g����u���Ԃɉ����ĕt�^�i����ɂ�1�_�j����܂��̂ŁA���m���Ɍ��荇�i���߂������ɂ͂����߂ł��B
����ɏ㋉�R�[�X���߂����������́u��ы��v����`�����X�ɂȂ邽�߁A�P�N�ȏ�p�����ĎQ������邱�Ƃ������ƂȂ�܂��B�܂��㋉���i�҂͓���̍u�t��g�X�[�p�[�o�C�U�[�h�ւ̐��E�E�F�肪����܂��B
�@���Q�l����⇒�@https://www.youtube.com/watch?v=uMBrpxG3JEo
�ڂ����m�肽�����͂��C�y�Ɏ����ǂɂ��⍇�����������B
�y�\���z�ȉ��̃t�H�[����肨�\�����݂��������B